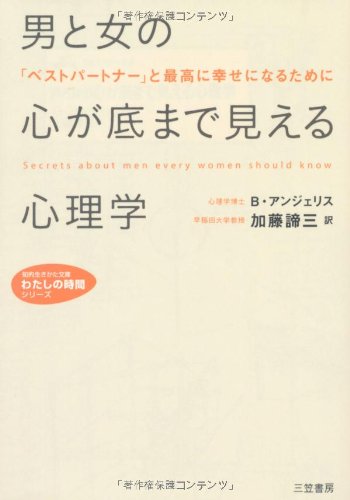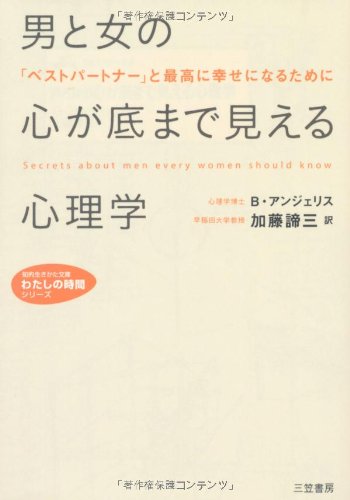
- 読みやすさ ★★★★☆
- わかりやすさ ★★★★☆
- オススメ度 女性★★★★★ 男性★★★☆☆
今日読んだ本はコレです!
試験前なので、大学の図書室で参考書を借りようと思ってパソコンで調べようと思っていたら、
前の使用者の履歴が残っていて、その本がコレでした。
なんとなく読んでたら思いのほか面白くて、全部読んじゃいました。
勉強してねぇ..
さて
今日は、本の内容を説明するんではなくて、僕が思ったことを書きたいと思います。
まず、借りて読んだ後に気付いたのですが、
コレ、僕が読むような本じゃなかったです。
タイトルが紛らわしいのですが、女性による女性のための本でした。
(パソコンでこの本調べてた人は男だったんですが…)
さらに言えば、「今の彼・夫ともっと幸せに暮らすには」的なことが書いてあるので、
お相手のいない男の子である僕には、イチバン遠い世界でした
(夜の営みについても詳しく書いてありました。モチロン、心理学的・学術的にキチンと書かれてますよ。)
ただ、男性の心理を説明してるトコロもあったんですが、
これが結構当たってます!(僕の意見ですが)
さて、細かく考えたことを綴っていきます。
相手への依存
この本の前半で「うまくいってない恋愛の事例」をイロイロ紹介しているのですが、
その女性たちに共通して言えるのが、相手に依存してしまっていることです。
(コレを読んでくれてる方の大半が「お前が言ってんじゃねぇよ!」と思ってるでしょうが、
今日は我慢してください)
相手の世話を焼きすぎること、相手の趣味に無理矢理合わせてること、
これらは、「相手を愛している」とアピールすることで、「相手に同じように愛してもらいたい」
との思いが表れていると思います。
裏を返せば、そういった行為で「奉仕」しないと自分を愛してくれない、という
「自身のなさ」があるということです。
このコトについて、色々と述べられていますが、
僕に言わせれば、
- 「自分に自信を持って生きるのが一番!」
- 「無理してまで付き合う必要はないでしょ!」
ってのに尽きます。
(これまた読者から「うっせぇ!ドーテー!」と言われてしまいそうなんですが…)
あと、この本には、
「自分が愛しているのと同様かそれ以上の愛を得るには」
なーんて書いてありますが、
そもそもそういった男女の付き合いを「損得」のものさしで測っちゃイカンでしょ!
どっちかは必ず少なくなっちゃうんだから!
相手に要求するんでなくて、相手への貢献それ自体に幸せを感じれたら
人生楽しいんじゃないかな。
「相手が自分に、なにも尽くしてくれなかったら哀しいじゃない」とか、
「そんなんじゃ相手に利用されちゃう」
なんて言ってる輩は、そんな杞憂をしなくてすむ人を探してください。
さて、後半になると話は代わって、
「男女の考え方の違い」です。
ちょっと心理学っぽくなってきました。
「そんなカンジの、前に読んだことあるわ」と思っても、新しい発見があったり、
知ってた知識の、より深い理解ができると思うので、損はないと思います。
一般に言われているらしい男女の違いはコチラ
男性
- 目的志向型
- セックスで愛情表現・自己の満足
- 何かしながら話すのが苦手
女性
- プロセス志向型
- ロマンス・会話・寄り添うことで愛情表現・自己の満足
- 何かしながらでも話ができる。
ってカンジらしいです。
普段の会話で行くと、
- 女性は、漠然と話し始め、話しながら考えを整理していく
- 男性は、あるゴールに向かって無言でじっくり考え、要点だけを端的に話す。
セックスで言えば、
- 女性は、前戯・触れ合うこと・ピロートークが大事
- 男性は、セックス自体が大事
ってことですかね。
ここも、異性の価値観の違いを理解する、ということが一番大事だね。
知らないと、「あの人は私を愛してない!」「わたしの事ちっともわかってない」
っていう誤解から、ケンカに発展するからね。
(お前が言ってんじゃ…以下略)
とまあ、色々書きましたが、
相手のことをキチンと理解して、尽くしてあげる。
自分にも自信をもって相手に認めてもらう。
そんな関係を築けたらいいですね。
ちなみに、僕は相手のことをキチンと理解しますし、愛しますよ!
女性の方、デートのお誘い待ってます。
最後に、僕がかなり笑った部分を、ちょっと編集してご紹介!
かなり下ネタで申し訳ないんですが、フェラチオの話です
「新しい彼ができたわ!名前はアンディ。素敵な人よ!」
「よかったじゃない!」
「ただひとつ問題があって、彼フェラチオ大好きなの。私はゾッとしてしまうわ」
「そう。ねぇ、私に任せて!いい案があるわ。」
「どうするの?」
「あなたの愛しのアンディが、15cmの小人になったところを想像してみて。
あなたは、そんな状態の彼をどうやって愛してあげる?」
「そうね…やさしく撫でて、キスして、好きってささやくかしら」
「結構よ。実はね、あなたのアンディは『小さなアンディ』を持ってるの。
そしてその背丈が15cmしかないのよ。あなたがその部分を愛してあげるとき、
あなたはただ、口にくわえるだけじゃない。『小さなアンディ』を愛してあげるのよ」
数日後、
「ありがとう!おかげで、アンディと最高の夜を過ごせたわ。
彼、驚いてたけど大喜びだった。
あなたには感謝してるわ。アンディにも感謝してるし、もちろん、『小さなアンディ』にもね!」
小さなアンディがどこにいようと、彼が幸福であることを私は願っている。
15cmとかうるせえよ!
最後の一文なんだよ!小さなアンディは常にアンディの股間にぶら下がってんだろ!
なんてツッコんでしまいました。